熱可溶化で発酵効率が大幅に向上したバイオガスプラントを開発
このたび三菱化工機株式会社(社長:波多野 怜、所在地:川崎市川崎区大川町2番1号)は、食品廃棄物を対象に、メタン発酵液をアルカリ・加熱処理により可溶化し、高温メタン発酵を行うことでメタンガスの発生量の増加と発酵残渣を減容化するバイオガスプラントを開発しました。

開発の背景
バイオガスプラントは有機性廃棄物から電力・熱エネルギーが回収できる再資源化施設として普及しつつあります。バイオガスの有効利用のため、メタンガスを高効率に発生させる技術および発酵残渣の処理が課題となっています。中核の発酵プロセスでは、中温発酵方式(37℃)が主流ですが、当社は課題解決のために高温発酵方式と可溶化方式を採用しました。
プロセス
本プラントのプロセスは破砕・貯留槽の前処理装置と、高温メタン発酵による発酵槽と、発酵廃液を濃縮しアルカリ・加熱処理を行う可溶化槽より構成されています。(図参照)
可溶化槽には、5~6%に濃縮した発酵汚泥が供給され、pH9~10、加熱温度80~120℃にて可溶化処理を行います。これにより汚泥中の有機物は低分子化し、高温メタン発酵槽へ返送することにより容易にメタンガスへ転換されます。同様に可溶化汚泥がガス化されるため引き抜き汚泥(発酵残渣)も減容できます。
テストの結果、可溶化がないプロセスに比較して、メタンガス発生量は、15%以上増加し、発酵残渣は70%以上低減できました。また、高温メタン発酵方式の採用により、中温メタン発酵方式に比較して、発酵槽容量は1/2以下に縮小できました。
一日あたり約5トン~100トンの処理規模に適応するプロセスです。
プロセスフロー
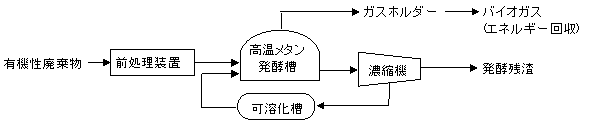
今後の展開
家畜ふん尿等の有機性廃棄物にも本プラントの適用を検討しています。家畜ふん尿処理では、メタン発酵槽でアンモニアによる発酵阻害が問題となっていますが、本プラントでは、可溶化槽でアンモニアを除去できるため、高温メタン発酵が適用できます。
家畜ふん尿処理に高温発酵を適用すると、ガス発生量の増加とともに発酵日数の短縮が図られ、省スペース化が図れ、かつ高効率のメタン発酵が可能となります。
バイオマスタウン構想のベースとして、また、有機性廃棄物の処理方法として、自治体に向けて本プラントの提案を行っていきます。
